 |
音羽山清水寺(きよみずでら) 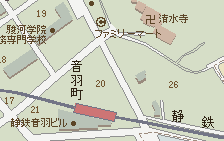 |
音羽山清水寺(きよみずでら)
 |
音羽山清水寺(きよみずでら) 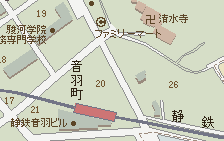 |
| 「案内看板(入口右側)の内容」 清水寺(音羽山清水寺) 清水寺は、永正年中(一五〇四〜)、印隔法印が開いた檀林(学問所)の古地に、当時今川八代守護大名氏輝の遺命によって永禄二年(一五五九)家臣の朝比奈丹波守元長が創建したものである。開山は、京都から迎えられた尊寿院大僧正道因と伝えられている。この地の眺望がすばらしく、京都の清水寺に似ていたので、その名がつけられた。境内には、慶長七年(一六〇二)徳川家康が建立した観音堂をはじめ、薬師堂、聖天堂・霊牌、金比羅神社、熊野神社などがある。観音堂の中には、同じ頃に建立されたと思われる禅宗様の宮殿型厨子が安置されている。いずれも安土桃山時代の建築様式を伝え、昭和三十一年五月に県の文化財に指定されている。また、清水寺境内は文学碑の宝庫でもある。初夏の駿河路を吟じた松尾芭蕉の有名な句である”駿河路やはなたちばなも茶のにほい”の句碑をはじめ、山村月巣、小林文母らの句碑が数多くある。樹木におおわれ、苔むした句碑が静寂な境内にひっそりとたてられており、いっそう歴史の重みを感じさせている。なお、当寺は規律の厳しい寺であるため、観音堂、薬師堂など、殿堂の一般公開はしていない。昭和五十八年十月 静岡市 |